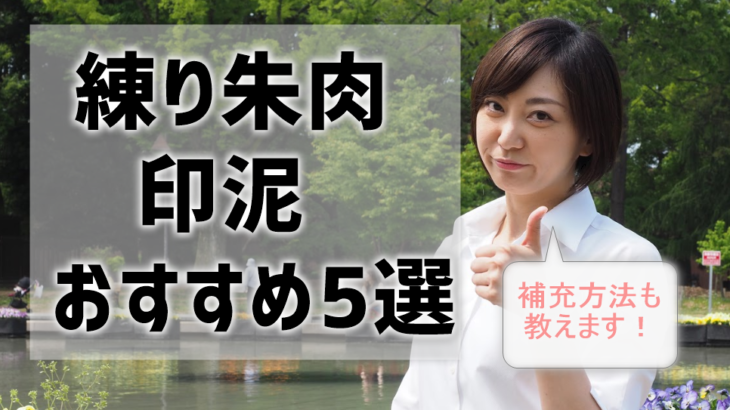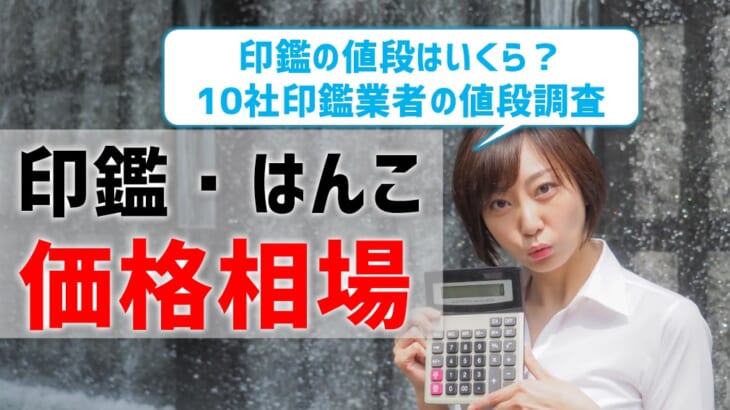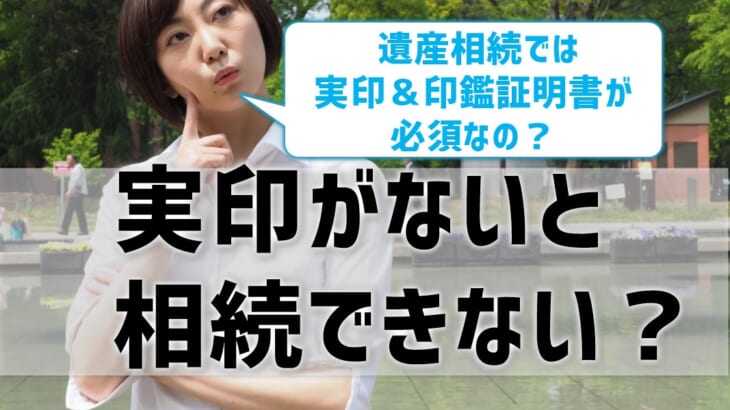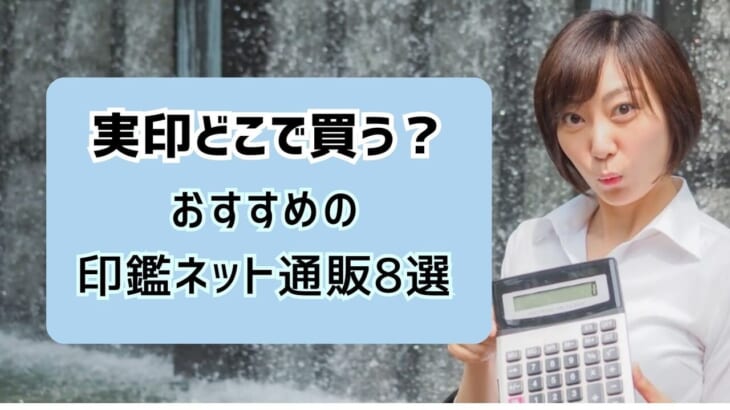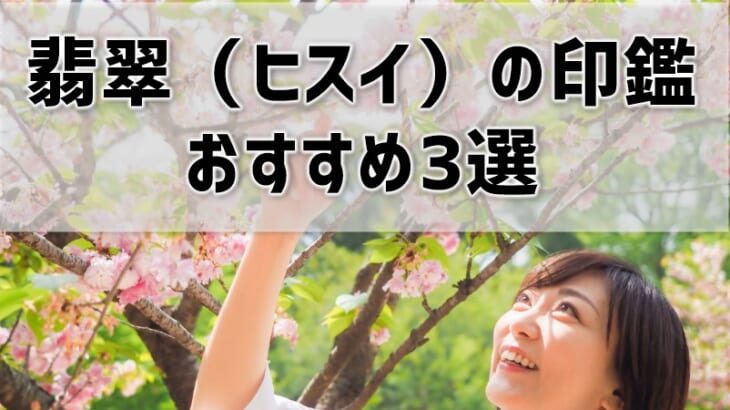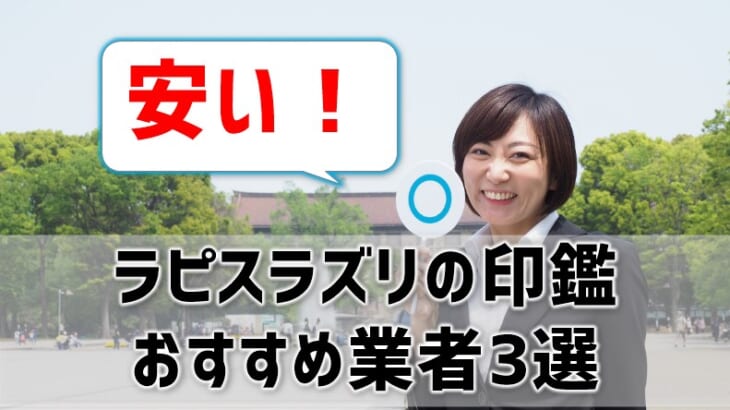新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 オペレーター 杏奈
オペレーター 杏奈
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 オペレーター 杏奈
オペレーター 杏奈
練り朱肉・印泥(いんでい)とは?
※画像はハンコヤドットコム公式より引用。
現代では便利に使えるスポンジ朱肉が主流ですが、朱肉の歴史をたどると練り朱肉や印泥にたどりつきます。速乾性や扱いやすさという点ではスポンジ朱肉に軍配が上がりますが、練り朱肉・印泥はスポンジ朱肉よりも濃く鮮やかな印影を得られます。印影の美しさにこだわる方には、スポンジ朱肉より練り朱肉・印泥がおすすめです。
練り朱肉と印泥の印影の美しさはほぼ同格ですが、発祥や成分は異なります。以下、練り朱肉と印泥の発祥と成分の比較です。
| 発祥 | 成分 | |
| 印泥 | 中国 | 硫化水銀系の珠砂+乾燥よもぎ+顔料+油 |
| 練り朱肉 | 日本 | 銀朱(硫化水銀)+ひまし油+木蝋+松脂+よもぎや和紙 |
練り朱肉は、中国の印泥を参考にして日本で製作されたものです。成分も若干違います。練り朱肉よりも印泥のほうが若干、ドロドロとしており扱いにくいため、上級者向けの朱肉です。
ただ、それ以外の性質はほとんど共通します。以下、印泥と練り朱肉の性質を列挙します。
- 濃く美しい印影
- にじみにくい
- 色褪せしにくい
- 容器が美しいものが多い
【デメリット】
- 乾きにくい
- 練り作業が必要
- 長期間放置するとカチコチに固まることもある
- 顔料と油が分離してベタベタになることもある
印泥・練り朱肉の魅力は、第一に印影の美しさです。スポンジ朱肉より濃く深い色合いを持つものが多く、印影自体の立体感も感じられます。また、にじみにくく、色褪せしにくいので、長期間の保存にも耐えられる点もメリットです。さらに、印泥・練り朱肉は、ケースも多彩。南部鉄器製のものや木製ケース、金属製ケースなど、オシャレで高級なものを好みで選べます。
このように印泥・練り朱肉は、朱肉として優れた性質を持ちますが、乾きにくさやお手入れの大変さがデメリットとして挙げられます。
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
捺印方法
印泥や練り朱肉を、スポンジ朱肉と同じように使うと、後のお手入れが大変になります。正しい捺印方法は以下です。
- 印泥・練り朱肉が入った器に手を添える。
- 印鑑を軽く持って、上下を確認する。
- 印鑑をポンポンと軽く朱肉につける。その際、朱肉の中央ではなく、端部分のみ円を描くように使う。
- 「の」の字を描くように捺印する。
ポイントは、朱肉の中央部分の山を壊さないよう、端部分のみを円を描くように使うということです。朱肉の中央の山が崩れると、朱肉を印鑑に付け辛くなります。山が崩れると練り直して、再度朱肉の形を整えなければなりません。朱肉の端部分のみを使えば、山が崩れることはなく、長期間練り直し無しで使用し続けることができます。
また、印鑑を朱肉に付ける際には、肩の力を抜いて、ボコボコとした穴を朱肉に開けないことが大切です。ポンポンとリズミカルに軽く付けるだけで、しっかりと朱肉は印面に付着しますので安心して使ってください。
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
手入れ・補充方法
印泥・練り朱肉の手入れ・補充方法をお伝えします。印泥・練り朱肉の手入れ・補充方法には、以下のパターンがあります。
- 定期メンテナンス
- カチコチに固まってしまった場合
- ベタベタに分離してしまった場合
それぞれのパターン別に具体的な方法をご紹介します。
定期メンテナンス
朱肉を手入れするには、金属ベラが必要です。金属ベラは必ずしも専用のものでなくても、大丈夫。バターナイフでも代用できます。朱肉のお手入れ方法は以下です。
- 金属ベラで朱肉を柔らかくなるまでほぐす。
- 形を整える。
- 金属ベラを火であぶるなどして温め、表面をならしていく。
- 朱肉中央部分を高く整えたら完成。
上記の作業は素人でも数分で完了します。慣れた方なら1分程度でできます。表面をできるだけ滑らかに整えることがポイントです。
カチコチに固まってしまった場合
朱肉がカチコチに固まってしまった場合、上記のメンテナンスでは元に戻りません。朱肉がカチコチに固まってしまった場合は、元に戻すのはほぼ不可能です。朱肉容器が気に入っているようなら、中身だけを新たに購入して詰め替えるのをおすすめします。
どうしてもリカバーしたい場合は、以下の方法を試してみましょう。
- カチコチの朱肉をナイロン袋に入れて、湯煎する。
- 火傷しないようにナイロン袋をお湯から取り出し、袋の上から朱肉を揉みこむ。
- 1~2滴程度専用補充インクを足して、袋の上からさらに揉みこむ。
- 柔らかくなったら、朱肉をナイロン袋から出してケースに戻す。
- 金属ベラでよく練り、形を整える。
朱肉は温めると柔らかくなるという性質があります。まず温めてみて、それでも硬そうなら、専用の補充インクを足します。印泥・練り朱肉の多くは、専用の補充インクがありますが、中には「インク補充不可」という商品もあるので注意しましょう。また、どの補充インクがいいか分からない場合は、「ヒシエム 朱の油」がおすすめです。
ベタベタに分離してしまった場合
朱肉がベタベタになって表面に油が浮いているような状態になった場合は、布などで表面に浮いた油分を吸い取ってしまえば再度使えるようになります。布でポンポンと朱肉表面を軽くたたくようにして油を吸い取ります。
そ一晩放置してみてそれでも油が浮いているようなら、同じ作業を繰り返します。その後、布を朱肉サイズに切り取り、一晩ほど朱肉表面に密着させて放置し、じっくりと布に油を吸わせます。
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
おすすめ5選
最後に、印泥・練り朱肉を使うのが初めてという方でも使いやすいと評判のおすすめ朱肉を5つご紹介します。
丸山工業 金龍 公用朱肉
丸山工業の「金龍」は、大変発色が鮮やかな最高級朱肉です。また、適度な弾力性があり、印鑑への朱肉の付きも良いので、初心者でも扱いやすいと好評。金龍は温度変化にも比較的強く、べたつきも少な目です。「公用」は家庭用に作られているため、価格が控えめなのも嬉しいポイント。
日光印 印泥
「練り朱肉ではなくぜひ中国伝来の印泥を試したい」という方におすすめなのが、日光印の印泥です。日光印の印泥は、長期間保存してもカチコチに固まってしまうことはありません。また、人体に有害な物質は一切使用しておらず、自然オーガニック素材というのも安心です。色味も「黄口」「赤口」「濃赤」の3種から選べます。
シヤチハタ 鯱旗印肉
- 長期保存しても固まりにくい
- 分離しにくくべたつきにくい
という、2点のメリットがあることから、練り朱肉初心者に人気があるのが、シヤチハタの鯱旗印肉。メンテナンスが非常に楽な練り朱肉です。高級有機顔料使用で、印影の鮮やかさも絶品!ちなみに、専用の補充インクも別売り販売されています。
印鑑本舗 高級朱肉・黄金朱肉
朱肉の質だけでなく、容器にもこだわりたいという方におすすめなのが、印鑑本舗から発売されている黄金の朱肉ケースに入った印泥。 美しい菊の文様が施された蓋ケースが素敵です。またさらに桐箱も付属し、プレゼントにも最適。朱肉自体は、昔ながらの印泥なので、お手入れを入念にしましょう。
サンビー 高級美術鉄器 練朱肉
伝統工芸の南部鉄器の容器におさめられた重厚感あふれる練り朱肉です。 普通の印鑑の捺印にはもちろんのこと、落款印にもおすすめ。南部鉄器の容器自体にある程度の重さがあるため、印鑑を朱肉につける際に不用意に動く…ということがありません。一生ものの練り朱肉をお探しの方におすすめです。
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
 オペレーター 杏奈
オペレーター 杏奈
まとめ
- 印泥・練り朱肉は、スポンジ朱肉より鮮やかな印影・にじみにくい・色褪せしにくい
- 印泥・練り朱肉は、スポンジ朱肉より乾きが遅い・メンテナンスがやや面倒
- 印泥は中国発祥、練り朱肉は日本発祥で、成分もやや違う
- 正しい捺印方法で、メンテナンスが楽になる
- 定期メンテナンスには金属ベラ・補充インクが必要
- カチコチに固まった場合は、中身買い替えがおすすめ
- べたつきは、布で油を吸い取る
- 印泥・練り朱肉は、容器もデザイン豊富