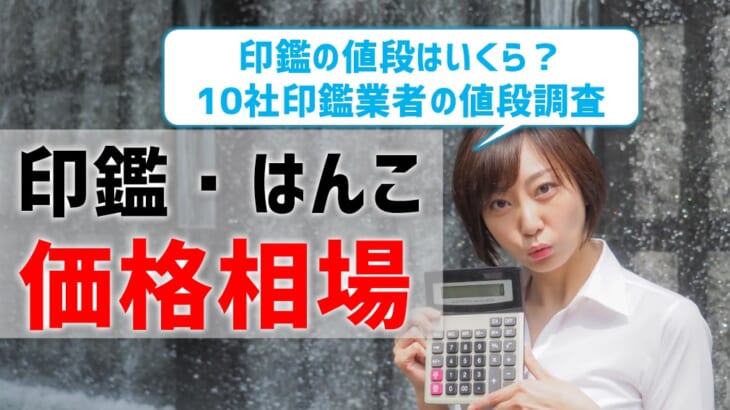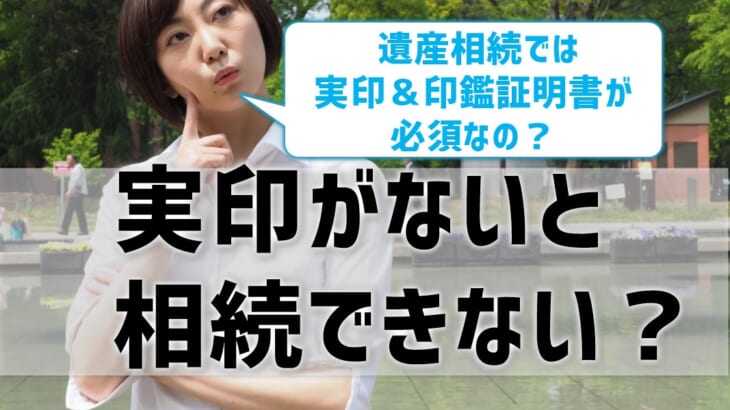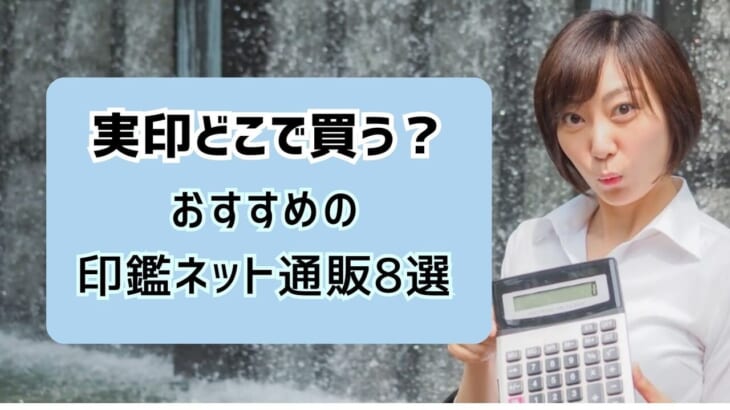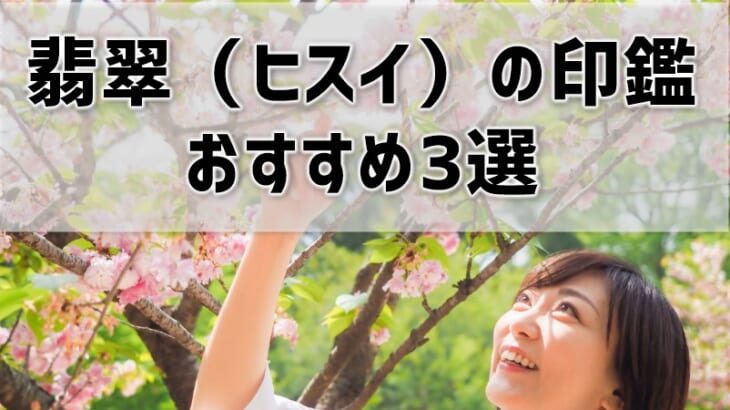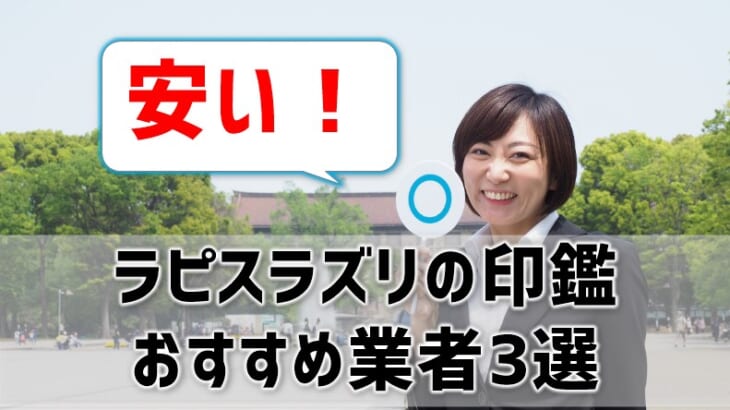「ハンコを押すのは苦手」という方は意外と多いようです。でもコツさえ身に付ければ、誰でもキレイにハンコを押せるようになります。ポイントは、朱肉とマット、そして力のかけ方です。今回は、印鑑の押し方のコツをお伝えします。
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川

準備ポイント3つ
かすれやにじみのない美しい印影を手に入れるには、準備が大切です。準備ポイントは以下の3つです。
- 印面がキレイなハンコ
- 捺印マット
- 朱肉
印面がキレイなハンコ
まずは、印面がキレイなハンコを準備しましょう。印面がキレイに整っていないと、どんなに気を付けて捺印したとしても、上手く捺印できません。まず印面のホコリチェックをします。印面にホコリなどが詰まっていると、文字がつぶれてしまったり印影がぼやけてしまったりと、はっきりとした印影を得られません。
また、印面の欠けがないかもチェックしましょう。印材によってはほんの少しの衝撃で印面が欠けてしまうことがあります。さらに、印面中央部が平らに整っているかも同時にチェックします。特に木材系の印材は、湿度・温度変化に敏感です。保管方法が悪いと、印面が変形してしまいますので、注意しましょう。
印鑑の保管は、保護・防犯がカギ!大切な印鑑を守るためにできること
捺印マット
「いつも上手く捺印できない」とお悩みの方はぜひ、捺印マットを準備してください。捺印マットとは、捺印時に用紙の下に敷くマットのことです。捺印マットはキレイに捺印できるよう、弾力性を考えて製作されています。捺印マットを敷くだけで、劇的に印影が変わることもあります。
捺印マットにはオシャレなものも多数あります。が、印影にこだわるなら、業務用の捺印マットがおすすめ。コクヨやサンビー、シヤチハタから発売されている王道の捺印マットなら、美しい印影に変わるはず!
捺印マットでキレイな印影を!おすすめは革製?ゴム製?大判?おしゃれなものも
朱肉
はっきりとした鮮やかな印影を目指すなら、朱肉選びも重要なポイントです。キレイな印影を得られないため、避けたい朱肉を以下に挙げます。
- 印鑑ケース付属の朱肉
- 100均朱肉
- スタンプ台の赤
手軽という理由から、印鑑ケース付属の朱肉をよく使うという方も多いようです。しかし、印鑑ケース付属の朱肉は、径も小さく、インクの量も少な目。さらにスポンジ面も粗悪なことが多いためNGです。また、100均の朱肉もメーカー品と比べると、インクの質やスポンジ面の質が劣ります。
そして、絶対に辞めたいのが、スタンプ台の赤を朱肉として使うこと。スタンプ台の赤は、水性インクを使っていることが多く、またゴム印を想定して作られているため、インクの付きが薄めです。スタンプ台の赤では、はっきりとした印影を得ることは難しいでしょう。
インクの質にこだわった朱肉を製作しているメーカー品を選ぶことが、美しい印影を得る近道です。おすすめのメーカーを列挙します。
- シヤチハタ
- マックス
- サンビー
- 新朝日コーポレーション
- 三菱鉛筆
- 日光印
- 丸山工業
朱肉には、スポンジタイプと練りタイプ、印泥があります。素人でも扱いやすいのはスポンジタイプです。それぞれの特徴を把握して、好みのタイプを選ぶといいでしょう。詳しくは、以下の記事を参照してください。
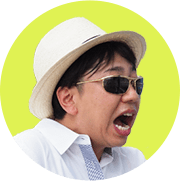 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
印鑑の押し方のコツ
まず、基本的な捺印方法を確認します。
- 印鑑の上下を確認して、親指・人差し指・中指の3つの指で印鑑を持つ
- 印鑑を朱肉に軽く3回「ポンポンポン」という感じでつける
- 姿勢を整え、印鑑を真上から「の」の字を描くようにゆっくり押す
- 捺印し終わったら、必ずティッシュなどで印面を拭っておく
まず、印鑑を3つの指でしっかりと持つことが大切です。印鑑自体がぐらぐらしていると、にじみやズレの原因になります。また、朱肉をつける際にぐりぐりと強めに押しつけてしまう方がいますが、これもNGです。朱肉に強く押し付けすぎると、朱肉が印面の枠の外にまでべったりとついたり、文字の彫りを潰してしまったりします。
そして、いざ捺印する際には、姿勢も大切。背筋を伸ばして肩の力を抜いて、楽な姿勢をとります。印鑑を支えるのが不安なら、利き手以外の手を軽く印鑑を持っている方の手に添えてもいいでしょう。準備が整ったら、真上から印鑑を押します。その際、上下左右に印鑑を軽く押す感じで捺印すると上手くいきます。「の」の字を描くようなイメージです。
そして無事に捺印し終わったら、必ず印面をティッシュなどで拭っておきましょう。印面に朱肉を残さないことが、印面をキレイに保つコツです。
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
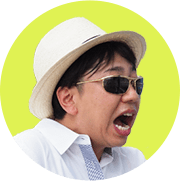 新人GメンKEICHI
新人GメンKEICHI
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
捺印性の高い印材
捺印性の高い印材で特におすすめなのは、以下の種類です。
- チタン・コバルトクロムモリブデン合金
- 黒水牛・オランダ水牛
チタン・コバルトクロムモリブデン合金
印材の中で最も捺印性が高いと言われているのが、チタンとコバルトクロムモリブデン合金です。チタンもコバルトクロムモリブデン合金も、大変粒子が細かく、朱肉のつきが良いのが特徴です。また、どちらも金属のため、ある程度の重さがあります。力を入れなくても、印鑑の重さに任せればキレイに捺印できるため、女性にもおすすめの印材です。
チタンは多くの印鑑ショップで購入可能ですが、コバルトクロムモリブデン合金は最新印材のため、ハンコヤドットコムでのみ購入可能です。また、チタン実印15mmの相場は13,000円~16,000円ですが、コバルトクロムモリブデン合金は24,140円とやや高め。興味がある方はぜひ、ハンコヤドットコムを覗いてみてください。
【ハンコヤドットコムの口コミ評判】実印や会社印の作成者必見!人気の印鑑通販サイト解説
【コバルトクロムモリブデン合金の印鑑の価格とデメリット】チタンより上⁉ 耐久性・捺印性がスゴイ
【チタン印鑑の価格とデメリット】コスパが高く実印・銀行印におすすめ!
黒水牛・オランダ水牛
動物系印材である黒水牛やオランダ水牛も捺印性が高い印材の一つです。水牛角に含まれるタンパク質が朱肉のつきを良くしています。牛角はチタンやコバルトクロムモリブデン合金よりははるかに軽い印材ですが、手への馴染みも良く、価格も安いため多くのユーザーに支持されています。
また、黒水牛・オランダ水牛よりさらに高い捺印性を誇る動物系印材といえば象牙ですが、現在、象牙の印鑑を手に入れるのは非常に難しく、価格も高めです。ぜひとも象牙を手に入れたいという方は、象牙のストックを持っている印鑑ショップへ問い合わせてみましょう。
【印鑑の素材・水牛の価格とデメリット】黒水牛とオランダ水牛の違いは?どちらも実印・銀行印に◯
【印鑑の素材・象牙の価格とデメリット】販売中止間近⁉ 希少で高価な”印材の王様”
まとめ
- 捺印前に、印面がキレイかどうかチェックを
- 捺印マット&性能の良い朱肉を準備
- 朱肉の正しい付け方=軽くポンポンポン
- 姿勢を正しく、「の」の字を描くように押す
- キレイに捺印できないようなら、印材から見直し検討を