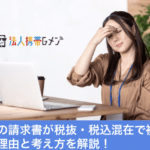業務用に配布した法人携帯ですが、もちろん利用者が所有し、持ち歩くためある程度本人が使いたいように使えてしまいます。
業務携帯の私的利用をどこまで認めるのかは、ケースバイケース。一般的な傾向や法人携帯Gメンの見解をお伝えします。
↓↓↓無料で相見積&しつこい営業無し↓↓↓
・法人携帯おすすめ比較(トップページ)
・法人携帯を安い料金で契約するコツ⇒⇒⇒法人携帯の「相対割引」とは?
・おすすめの法人スマホ⇒⇒⇒法人向けiPhone、法人向けAndroid
・法人携帯におすすめのガラケー
・おすすめの法人向けタブレット⇒⇒⇒法人向けiPad
・3大キャリアの説明⇒ドコモ、au、ソフトバンク
どこまでが個人利用(私的利用)かは企業の方針次第
結論としては、どこまでを個人利用(私的利用)とみなすかは、実はなかなか線引きが難しいです。結局のところ、企業の考え方次第という部分も大きいので、通話、データ通信に分けて例をみてみましょう。
通話の個人利用(私的利用)
たとえば、以下のようなケースどれが私的利用でしょうか?
- 災害時の家族への連絡に繋がりにくいMVNO(格安SIM)の個人携帯ではなく社用携帯を使った。
- 個人携帯が従量課金でもったいないので、恋人との電話は会社のかけ放題の携帯からしている。
- 40人単位の会社の忘年会の予約で、店からの連絡にもすぐ対応するために業務携帯でやり取りをした。
- クレジットカード会社への問い合わせに、ナビダイヤル(0570)はかけ放題の対象外なので電話代節約のため、業務携帯からかけた。
- 同期数名でのほとんどプライベートな飲み会の店の予約を、個人携帯を取り出すのも面倒なので業務携帯から行った。かけ放題だし特に問題はないだろう。
- 海外にいる友人宛に、会社携帯から国際発信した。1回っきりだし何か言われたら海外のお客様との連絡だったと言おう。
 新人Gメン及川
新人Gメン及川
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
携帯どこに置いたかわからなくなって業務携帯から私用携帯を鳴らして置き場所に気付く。それで私用携帯を開いた時、あ!着信きてる誰だろ!とか毎回思っちゃうんだけどどうしよう。
— あゆか (@ayu0308) November 23, 2011
 新人Gメン及川
新人Gメン及川
繰り返しですが、結論として絶対的な正解があるわけではありません。個人での利用は絶対に許さない、というところもあれば、会社に負担がかからない範囲(かけ放題対象内)で好きに使っていいという企業まで様々。
管理者の目線で考えれば「性善説で様子見をしながら怪しい利用者だけチェックする」のが楽です。気になるユーザーについては通話明細を取得し、詳細を確かめることができます。
データ通信の個人使用(私的利用)
データ通信においてもより、どこまでを個人利用(私的利用)とするかは判断が難しい所です。
- Youtubeを見るのに使っている
- 業務のために入れた「乗換案内」を休日はプライべートで使用している
- 業務用に入れたチャットアプリを、仲のいい同僚との休日の連絡手段にしている
- 休日も含め、毎日ニュースを見るためにインターネットに接続している
- お客様とのやり取りをプライベートな内容も含めてLINEで行っている
 新人Gメン及川
新人Gメン及川
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
データ通信は、音声通話にも増して業務利用なのか私的利用なのかが難しいところがあります。
また、会社が契約したデータを使ってYoutubeを見ることは私的利用と捉えても違和感がありませが、会社が貸し出した端末を介してWi-Fi環境でYoutubeを見ることは?と言われるとちょっと解釈が分かれそうです。
結局のところ、これも企業の考え方次第ということになってしまいます。
仕事仲間には私用スマホの番号やアドレス教えてあるけど、仕事の内容は送るなと言ってある。何か起きたときに疑われたくないからね。業務携帯は別にあるし。
私用教えてあるのはアフターファイブ(死語?)の飲み会連絡用w— ぶたまる ? (@JQ1BWT) July 4, 2019
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
MDM(モバイル・デバイス・マネジメント)で端末の制限が可能
対策としては、MDM(モバイル・デバイス・マネジメント)のシステムを導入することにより
- 特定のサイトにアクセスできない(ブラックリスト)
- 特定のサイトにしかアクセスできない(ホワイトリスト)
- そもそもインターネットにはアクセスさせない
など、機能制限を設けることや、通信履歴を閲覧することが可能です。会社のポリシーに応じて、使い分けてみてください。
 新人Gメン及川
新人Gメン及川
 ベテランGメン園川
ベテランGメン園川
まとめ
結局のところ「企業次第」というしかないので、絶対の正解があるわけではありません。ただ、法人携帯Gメンの見解としては、せっかく配布した端末は使いこなしてこそ、真価を発揮するというもの。
会社のお金を露骨に使ったり、就業時間を使って余計なことに時間を割いているような状態でなければ、ある程度の部分は黙認した方が管理者もユーザーも楽なのではないでしょうか?
運用してみて問題があるようであれば、MDMなどを用いた機能制限も可能なので、まずは柔軟に運用してみるのがおすすめです。
最終判断は、各企業様次第なので、ポリシーや業務内容に合わせて最適な形を追求してみてください。
↓↓↓無料で相見積&しつこい営業無し↓↓↓